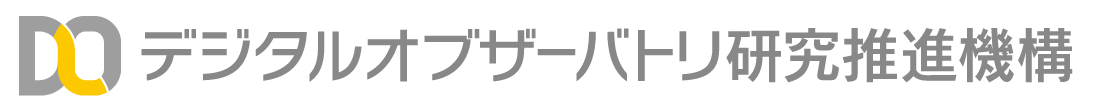デジタルオブザーバトリ研究推進機構フォーラム開催報告
2025年3月17日(月)、デジタルオブザーバトリ研究推進機構第2回フォーラム 「DO技術の生成AI活用による進展とサプライチェーンレジリエンスへの展望」を、東京大学山上会館大会議室及びオンラインによるハイブリッド形式で開催しました。
当日は、東京大学・株式会社日立製作所、両組織の構成員を始め、様々な企業、研究機関、官公庁関連の皆様から多数のお申込をいただき、約155名(会場参加:65名、オンライン参加:90名)の方にご参加いただきました。
喜連川優機構長及び阿部淳執行役副社長の冒頭挨拶で、東大としても今までにない規模で分野横断的に、かつ日立製作所も長年にわるデータベース事業で培ってきた知見を活かし、生成A Iなど新しい技術を活用しつつ,リスクの把握・予兆発見のための研究を共同で進めているとの挨拶がありました。


引き続き、第1部として、まず日立・東大側の9つの研究グループから、下記のとおり研究発表が行われました。
第1部:研究発表、パネルディスカッション
1.デジタルオブザーバトリ研究によるサプライチェーン強靭化に向けた取り組み
西澤 格 日立製作所 執行役常務CTO 兼 研究開発グループ長リスクの可視化と予兆を可能にする技術の開発を目指し、企業内外の多様なデータを統合・解析する中で、サプライチェーン上の脆弱ポイントとして、二次以降のサプライヤの製造拠点の把握に関する技術を開発したとの報告がなされました。また、最大級の日本語LLM(Large Language Models)が稼働可能なLLM実験環境を、東京大学駒場オープンラボラトリーに提供したことも紹介されました。

2.デジタルオブザーバトリ研究推進機構の概要と社会活動観測基盤
豊田 正史 東京大学 生産技術研究所 教授・東京大学デジタルオブザーバトリ研究推進機構 副機構長機構の全体像についての説明のほか、多様な社会活動を観測可能にする基盤構築の一環として、国際産業通関表のデータを用いたサプライチェーンの可視化分析システムと、LLMを用いて貿易統計データから、異常な動きを検知し説明するシステムを紹介したほか、農作物の供給安定化に向けた分析も進めているとの報告がなされました。

3.テキスト情報源からの武力紛争リスクの予測と説明生成
宮尾 祐介 東京大学 大学院情報理工系研究科 教授ニュースなどのテキストからリスクイベントを自動検出・予測し、その影響に関する説明を自動生成する技術の研究を行っており、社会科学の視点から武力衝突などのリスクイベントの定義とデータ収集を担当する阪本拓人教授のグローバル社会リスク分析チームとともに、リスクの検出・予測・説明を自動化する包括的なシステムの実現を目指しているとの報告がなされました。

4.貿易規制に起因するサプライチェーンリスクの予兆把握
伊藤 一頼 東京大学 大学院法学政治学研究科 教授塩尻 康太郎 東京大学 大学院法学政治学研究科 客員准教授第一次トランプ政権時の事例の分析を元に、規制発動の前後のニュース中の関連キーワードの出現頻度上昇などに予兆検知の可能性が示された他、生成A Iを活用した予兆把握の初期的研究を行い、キーワードの内容や出現頻度、フェーズ別のリスクレベルなどをリスクスコア化し、総合的なモニタリングを行うことで、企業が貿易リスクに備えられる仕組みの構築をめざしているとの報告がなされました。


5.船舶・貿易データ分析のためのUI
山口 利恵 東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授リアルタイムで取得可能なAIS(Automatic Identification System:船舶自動識別装置)データを用いた船舶動態を分析し、これに海洋系のニュースを関連づけて分析することにより、航行パターンや異常事態を把握できることが示されたとのことでした。今後の取り組みとして、ニュースやAISデータを自動で収集し、その影響を可視化するアルゴリズムの構築を検討しているとの報告がなされました。

6.食料安全保障に向けたグローバルサプライチェーン分析・農業生産リスクの空間解析・遺伝解析
岩田 洋佳 東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授食糧安全保障チームは、40%未満にとどまる日本の食料自給率の低さ、気候変動や社会環境の変化などの課題を背景に、グローバルサプライチェーンの分析、農林水産リスクの空間解析、遺伝解析を三つの柱として研究を行っており、日本の食料供給における海外依存の実態の可視化、災害リスクとその実態を可視化するシステムの構築、気候変動などのリスクに強い品種の開発などに取り組んでいるとの報告がなされました。

7.サプライチェーンレジリエンス一般均衡分析
古澤 泰治 東京大学 大学院経済学研究科 教授サプライチェーンの脆弱性やトランプ政権による関税政策のような政策ショックが、各国の生産・所得・CO₂排出量に与える影響を、世界の産業連関表などのデータを用いて分析している他、気候変動による災害増加などの生産への逆影響も考慮した双方向モデルの構築や災害時の都市の人流変化と都市設計のレジリエンスに関する研究も予定しているとの報告がなされました。

8.気候変動とその適応策が社会経済活動に与える⻑期的な波及効果を推計するための基礎的開発
川崎 昭如 東京大学 未来ビジョン研究センター 教授気候変動とその適応策が、世界特にグローバルサウスの社会経済活動に及ぼす長期的な波及効果を明らかにするための基礎的枠組みの研究をしており、洪水災害の適応策が住民のリスク認知や行動を変容させ、地域の社会経済活動に好循環をもたらすメカニズムをモデル化し、IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)の将来予測を活用してその効果を定量的に評価する枠組みを構築しているとの報告がなされました。

9.障害インクルーシブな組織の条件―企業・大学・行政機関を対象に―
熊谷 晋一郎 東京大学 先端科学技術研究センター 教授東京大学における多様性包摂の取り組みの一環として、学内の心理的安全性に関する調査や障がいを持つ構成員の面談記録データの分析などを通じ、ガイドラインの整備とデジタル技術を活用したインクルーシブモニタリングシステムの構築に取り組んでいるとの報告がなされました。

各研究チームの発表の後には、「サプライチェーンレジリエンスに向けた『データ×生成AI』への期待と展望」と題し、サプライチェーンの実務・政策に関わる産官学の有識者によるパネルディスカッションを行いました。
各パネリストからは、サプライチェーンの範囲の広さ、その複雑さからリスク把握をすることが困難であること、また可視化・予兆把握のために必要なデータの取得とその共有が、データ活用に共通する課題であるとの発言がなされるとともに、生成A Iなどの技術的知見を存分に取り入れながら、データ共有を視野に入れたシステム設計を推進するなど、デジタルオブザーバトリ研究を発展させていきたいという共通認識が示されました。


第2部:ポスター展示・ネットワーキングセッション
第2部では、各研究チームの研究成果をまとめたポスター展示・発表を行い、中長期的な取り組みに向け、課題・ユースケース抽出から社会実装・ビジネス創出を視野にいれた企業・機関との連携を探索するためのネットワーキングセッションを開催しました。
現地開催された第2部ネットワーキングセッションにおけるポスター展示の様子
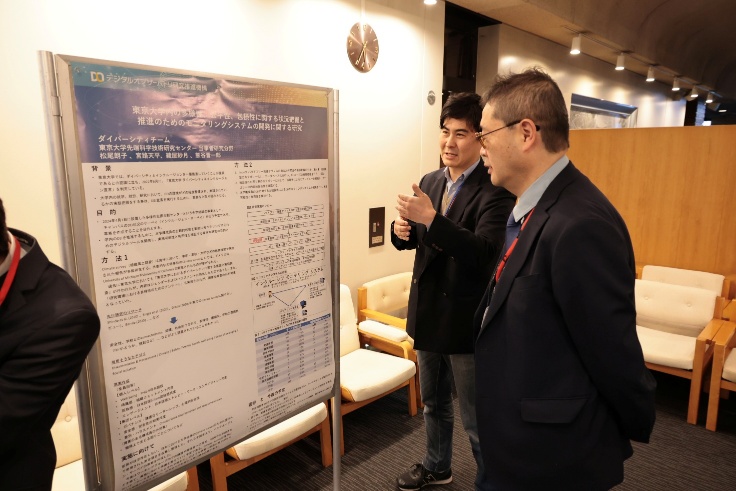
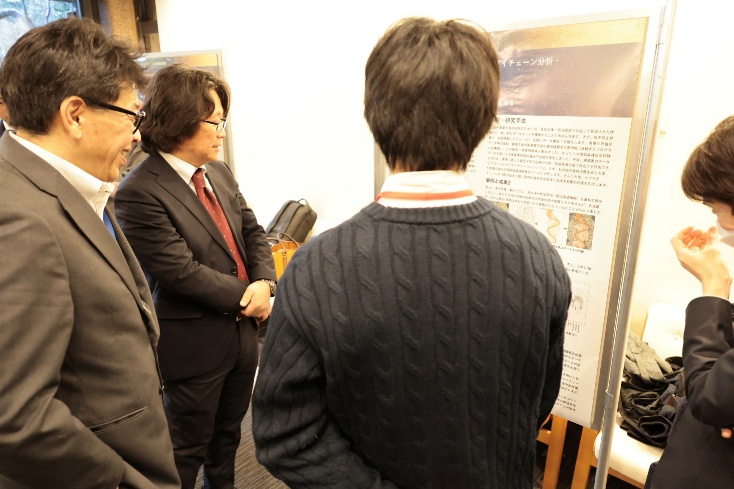

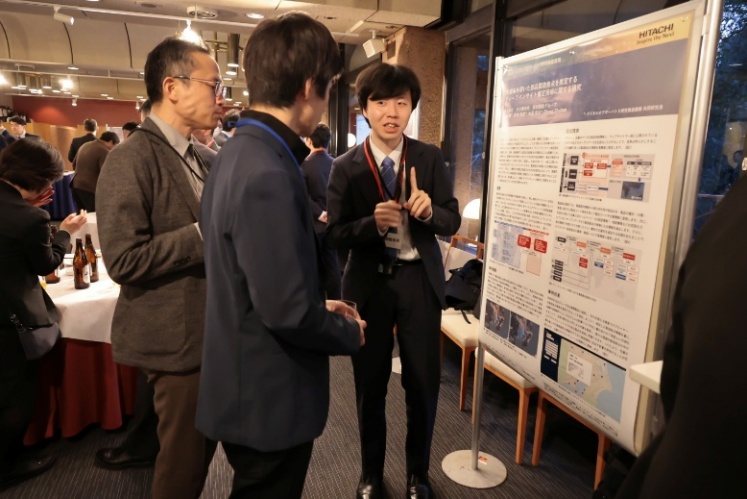

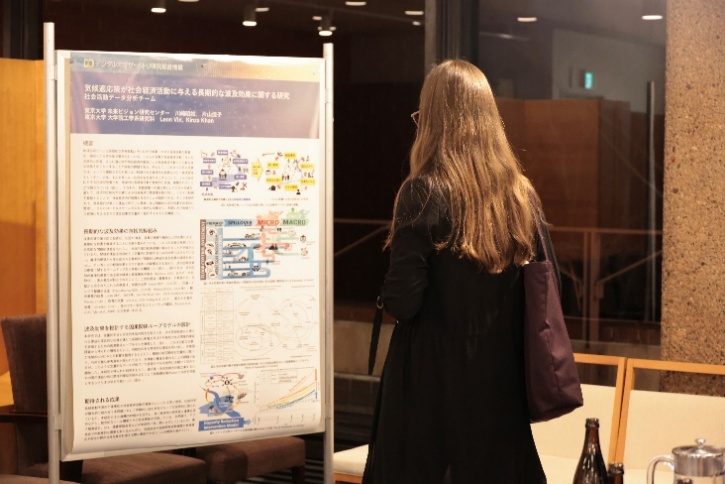

フォーラム全体、パネルディスカッションについての事後のアンケートでは、多くの方々に「非常に良かった」とご回答いただきました。以下、アンケートの一部です。
- 分野を横断して取り組みを知ることができて非常によかった。
- プレスリリースで興味を持ったディープインサイト推定技術について、理解を深めることができた。また企業や業界を跨いだデータ連携について、他の団体における現状の取り組みを聞くことができた。
- クオリティの高い話が聞けて、とても勉強になった。
- パネルディスカッションでは、実務的なものや新たな知見を得ることができた。
- 官学連携に向けた必要性がわかり、今後の取り組みに期待できる。
あらためまして、ご参加下さいました皆様、並びに開催にあたりご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。
※登壇者の所属・役職は,2025年3月時点のものです。
フォーラムフライヤー
本フォーラムの詳細は以下リンクからご確認いただけます。 フォーラムフライヤー(PDF)へのリンク