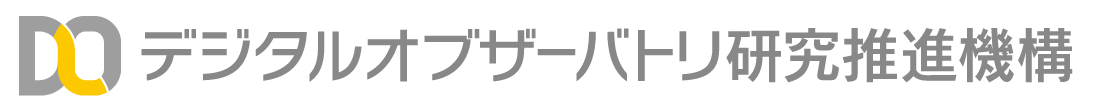研究テーマ・グループ Research Themes and Groups
利活用に関する研究グループ「食料安全保障チーム」
研究リーダー:岩田 洋佳(農学生命科学研究科・教授)
研究テーマ:我が国の食料安全保障をめぐる国内外のリスクの現状と要因
わが国のカロリーベースの食料自給率は2000年前後から約4割を上回ることがなく、食料を海外に大きく依存し続けています。国際的な食料マーケットの状況は、90年代以降の新興国の経済成長による食料需要の増大、気候変動による穀物生産の不安定化、国際紛争による地政学的リスクの増大などが進み、また食料だけでなく肥料や飼料なども海外に多く依存していて、わが国の食料安全保障を脅かす多くの懸念材料があります。以上のことを踏まえながら、海外からの食料調達、国内の食料供給をめぐる課題の解析と将来の展望を行います。
■グローバル・サプライチェーン分析グループ
グローバルな視点から食料サプライチェーンの分析を行い、わが国の食料安全保障に及ぼす影響を数量的に解析します。第一の課題は、わが国の食料消費を支えている国や産業がどのように変化してきたかを、国際産業連関表をベースに経時的に分析することです。グローバル・サプライチェーンの寸断が国内の食料安全保障に及ぼす影響を評価するためには、輸入先の分析だけでは不十分であり、国内の農業・食料生産のレスポンスも重要となります。そこで、第二の課題として、国内産業連関表をベースにした応用一般均衡分析により、国内経済を対象に輸入寸断の影響を分析し、第一の課題を補完します。なお、これら二つのアプローチは異なる前提条件に依存しているため、第三の課題として、海外と国内を同一の前提でコンシステントに分析できるモデルを構築し、分析の精緻化を図ります。
■国内生産データ構築・経済分析グループ
気候変動や農業の担い手減少・高齢化の中での圃場レベルの食料供給リスクを統計・経済学的側面から分析します。従来の農業生産リスクに係るデータは行政区分ごとに集計・平準化されていることが多く、局所的な災害や獣害も多い農業生産のリスクや要因について、精緻に把握すること困難でした。本グループは、NOSAI(農業共済)の被害収量データを用いて、圃場単位での高い粒度で自然環境や農業経営環境、様々なリスクが農業生産に与える影響の定量的評価を目指します。これは、NOSAIデータが、実際の農家の生産、圃場ごとに被害種目や減収を記録、平成31年度までほとんどの農家が加入、といった解析上優れたビッグデータであることから可能となる研究です。NOSAIデータは、詳細かつ固有の分類がなされた巨大なローデータであり、そのデータの外部データとの接続は容易ではありません。本研究ではAI等も用いて圃場データの適切で効率的な接続を試み、行政のアナログデータのデジタル化・保存手法への寄与も並行して目指していきます。
■収量リスク予測・育種データ解析チグループ
近年、台風や酷暑などの異常気象により農業生産への影響が拡大しています。品種ごとの異常気象への適応性には大きな差があり、育種時の栽培試験でもその兆候が確認されていると考えられますが、生産現場での実際のパフォーマンスを育種現場に定量的にフィードバックし、活用する仕組みは整備されていません。収量リスク予測・育種データ解析チームでは、NOSAIの被害収量データをWAGRI(農業データ連携基盤)の環境データや作物生育モデルと統合し、潜在収量との差から被害程度を定量的に評価することで、品種ごとの適応性を詳細に分析します。さらに、この適応性を育種時のデータやゲノム・血縁度データと組み合わせ、災害に強い品種を効率的に育成する予測モデルを構築します。このモデルを活用することで、異常気象下でも安定した生産が可能になり、食料安全保障や農業の持続性向上に貢献するだけでなく、次世代の革新的な育種技術の発展にもつながると期待されます。